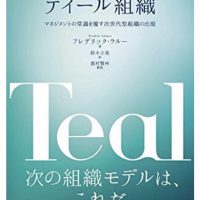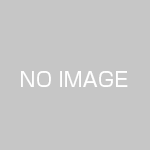私は発問自体を今まで知らなかったので・・・、先に補足いたします。
—
「発問」は子供の思考・認識過程を経るもの。
「質問」は子供が本文を見ればわかるもの。
文部科学省HPより
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/002/003/002/004.htm
—
というわけで、今回は学校教育者向けの書籍を活用します(ので「子ども」という言葉も出てきます。)
良い発問の特徴
発問された子どもが、自ら進んで答えたくなる、そして、その発問に答えると
新たな学びや気づき、行動がある発問。
「過去」よりも「未来」のことを聞く発問、
「クローズド・クエスチョン」よりも「オープン・クエスチョン」
※はい・いいえで答えられるのがクローズド。
「本当に手に入れたいもの」を聞く発問
「勉強の大儀」を聞く発問
「言葉の意味」を聞く発問
「反対の概念」を聞く発問
「当たり前と思っていること」を疑う発問
「立場を変えてみる」発問
「今と未来」について聞く発問
『「発問」する技術』(栗田正行:著)p136
感想
学校教育者むけの書籍なので、自分事に変換して考える必要がありますが、
親であれば、家庭内で子どもの教育、しつけに使えそうですし、
組織であれば、部下の教育に
自分に投げかければ、思考停止を回避し自己を再認識することに使えそうだと思いました。
こういう時間がかかりそうなコミュニケーションが
後々活きてくるんでしょうね。