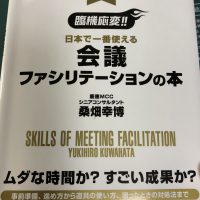日本が直面している急速な高齢化の進展は、疾病構造の変化を通じて、必要と
される医療の内容に変化をもたらしてきた。平均寿命 60 歳代の社会で、主に青
壮年期の患者を対象とした医療は、救命・延命、治癒、社会復帰を前提とした「病
院完結型」の医療であった。しかしながら、平均寿命が男性でも 80 歳近くとな
り、女性では 86 歳を超えている社会では、慢性疾患による受療が多い、複数の
疾病を抱えるなどの特徴を持つ老齢期の患者が中心となる。そうした時代の医療
は、病気と共存しながらQOL(Quality of Life)の維持・向上を目指す医療と
なる。すなわち、医療はかつての「病院完結型」から、患者の住み慣れた地域や
自宅での生活のための医療、地域全体で治し、支える「地域完結型」の医療、実
のところ医療と介護、さらには住まいや自立した生活の支援までもが切れ目なく
つながる医療に変わらざるを得ない。ところが、日本は、今や世界一の高齢国家
であるにもかかわらず、医療システムはそうした姿に変わっていない。
社会保障制度改革国民会議 報告書
~確かな社会保障を将来世代に伝えるための道筋~
平成25年8月6日
社会保障制度改革国民会議
21項
ダウンロード:首相官邸HP
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kokuminkaigi/
感想
平成25年 = 2013年
私にとっては最近話題と感じる用語「地域包括ケア」も
実は5年前には既に取り上げられていたんですね。
医療ニーズに対して供給能力が足りていないことは理解しつつありますが、
供給の体制にも未だ課題があるように感じています。
今回のような公の情報や、書籍を通じて
もっと国内の医療・介護の理解を深めていくことが
誰にとっても生活に関わるので大切だと思います。
◆蛇足
同資料の2項(1項は表紙)は下記のように始まります。
—
国民へのメッセージ
日本はいま、世界に類を見ない人口の少子高齢化を経験しています。65 歳
以上の高齢人口の比率は既に総人口の 4 分の1となりました。これに伴って
年金、医療、介護などの社会保障給付は、既に年間 100 兆円を超える水準に
達しています。
この給付を賄うため、現役世代の保険料や税負担は増大し、またそのかな
りの部分は国債などによって賄われるため、将来世代の負担となっています。
—
最近、この論理に疑問があります。
とくに、国際が負担になるという部分。
本当に負担なの?と思うのです。
説明は長くなりますのでしませんが、
社会が前提と認識しているであろう理屈も
確認することが大切と思い、調べてみると
いろんな説が出てくるからです。
ともあれ、診療・介護報酬は実際に改定され
益々地域包括ケアの促進に迫られているようですので、
(外側の知識も勉強しつつ)
足元の課題に行動していくことが大切と思います。